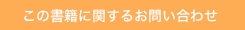戦国期越中真宗教団史論 金龍教英遺稿集

各門流の地域的偏差、諸寺の類型分け、消息法語の分別など新しい分析手法と多数の新史料の発掘で著名な師の史論から、論点・視点・切り口が後学の者に影響を及ぼし得る十編を厳選、史料遍を付して一冊に。真宗史研究者には必携。
- 著 者:
- 金龍静 編
- 定 価:
- ¥3500(税込:¥3850)
- 発行日:
- 2025.11.10
- ISBN:
- 978-4-86627-170-5
- 判 型:
- A5
- 頁 数:
- 320 頁
目次
刊行に寄せて
論文編
第一章 越中念仏者のあゆみ
第一節 綽如・蓮如上人と越中
第二節 実如・証如・顕如宗主時代
第三節 教如・准如宗主時代
第二章 高木場坊本尊の意義
はじめに 新出の裏書
第一節 土山坊と蓮誓
第二節 土山坊・高木場坊と実玄
むすび
第三章 梅原の以速寺
第一節 以速寺の由緒
第二節 梅原の地
第四章 真宗と五ヶ山
第一節 本願寺と五ヶ山
第二節 十日講と本願寺勤仕
第三節 戦国期の五ヶ山
第五章 大永五年赤尾三村掟について
第一節 三カ条の掟
第二節 実如の三カ条の掟
第三節 大永五年の掟の背景と赤尾三村
第四節 終りに
第六章 仏法と王法のあいだに―「京都」と石山本願寺―
一 仏法領とは
二 京都・京都様
三 大坂拘様
四 近世五ヶ山の仏法領
五 本覚寺門徒の意味
第七章 蓮照寺と堀秀政
一 新史料紹介と堀一族
二 史料⑤について
三 史料⑥について
四 まとめ
第八章 砺波郡の真宗寺院の展開
はじめに
第一節 郡内各市町村の寺院数・開基年の特徴
第二節 番役を担った寺・坊主の村の役家数
第三節 番役を担った寺・坊主の村の石高
第四節 まとめ
第九章 近世真宗寺院成立史考
第一節 はじめに
第二節 西方への木仏下付
第三節 東方への木仏下付
第四節 上寺と末寺の地域的特徴
第五節 近世寺院成立の様相
第十章 真宗寺院五尊御免について―富山藩西方寺院と専光寺末―
第一節 寺院化と五尊
第二節 近世の五尊下付規準
第三節 五尊下付順による寺院類型化
第四節 各法物の礼金
第五節 東本願寺系寺院の五尊下付の特徴
第六節 終りに
史料編
第一章 各寺所蔵文書の解説と目録
第一節 福岡町加茂超願寺文書 解説と目録
第二節 上平村道善寺文書 解説と目録
第三節 高岡市長光寺文書 解説と目録
第四節 井波町藤橋仏厳寺文書 解説と目録
第五節 福光町舘妙敬寺文書 解説と目録
第二章 採訪史料遺宝
解題
史料紹介
金龍教英氏 執筆業績
金龍教英氏 経歴
父のこと
兄の思い出
あとがき
論文編
第一章 越中念仏者のあゆみ
第一節 綽如・蓮如上人と越中
第二節 実如・証如・顕如宗主時代
第三節 教如・准如宗主時代
第二章 高木場坊本尊の意義
はじめに 新出の裏書
第一節 土山坊と蓮誓
第二節 土山坊・高木場坊と実玄
むすび
第三章 梅原の以速寺
第一節 以速寺の由緒
第二節 梅原の地
第四章 真宗と五ヶ山
第一節 本願寺と五ヶ山
第二節 十日講と本願寺勤仕
第三節 戦国期の五ヶ山
第五章 大永五年赤尾三村掟について
第一節 三カ条の掟
第二節 実如の三カ条の掟
第三節 大永五年の掟の背景と赤尾三村
第四節 終りに
第六章 仏法と王法のあいだに―「京都」と石山本願寺―
一 仏法領とは
二 京都・京都様
三 大坂拘様
四 近世五ヶ山の仏法領
五 本覚寺門徒の意味
第七章 蓮照寺と堀秀政
一 新史料紹介と堀一族
二 史料⑤について
三 史料⑥について
四 まとめ
第八章 砺波郡の真宗寺院の展開
はじめに
第一節 郡内各市町村の寺院数・開基年の特徴
第二節 番役を担った寺・坊主の村の役家数
第三節 番役を担った寺・坊主の村の石高
第四節 まとめ
第九章 近世真宗寺院成立史考
第一節 はじめに
第二節 西方への木仏下付
第三節 東方への木仏下付
第四節 上寺と末寺の地域的特徴
第五節 近世寺院成立の様相
第十章 真宗寺院五尊御免について―富山藩西方寺院と専光寺末―
第一節 寺院化と五尊
第二節 近世の五尊下付規準
第三節 五尊下付順による寺院類型化
第四節 各法物の礼金
第五節 東本願寺系寺院の五尊下付の特徴
第六節 終りに
史料編
第一章 各寺所蔵文書の解説と目録
第一節 福岡町加茂超願寺文書 解説と目録
第二節 上平村道善寺文書 解説と目録
第三節 高岡市長光寺文書 解説と目録
第四節 井波町藤橋仏厳寺文書 解説と目録
第五節 福光町舘妙敬寺文書 解説と目録
第二章 採訪史料遺宝
解題
史料紹介
金龍教英氏 執筆業績
金龍教英氏 経歴
父のこと
兄の思い出
あとがき