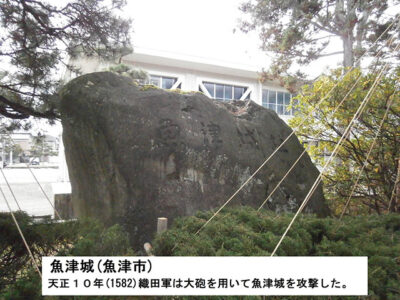佐伯哲也のお城てくてく物語 第5回
佐伯哲也の お城てくてく物語
第5回 埋蔵金伝説はほぼウソ?
全国の城には、掃いて捨てるほど多くの埋蔵金伝説が残るが、ほとんどウソといっても過言ではない。実績もそれを雄弁に物語っている。というのも今日まで約1万ヶ所の城で発掘調査が実施されてきたが、ただの1ヶ所も埋蔵金は出てこなかったからである。これでは埋蔵金伝説はほぼウソと言われても仕方なかろう。幻の白川郷帰雲城(岐阜県)の埋蔵金は、数百億円とも言われ、探し始めて60年以上経過しているが、見つかる気配すらない。興味は尽きないが、週刊誌向けのネタでしかなく、空しさすら感じる。
そもそも論になってしまうが、中世城郭から大判小判が出る可能性は極めて少ない。というのも大判小判は、豊臣秀吉が天正15年(1587)貨幣制度を定めてから世の中に出回ったのであり、それまでは宋銭と呼ばれる中国貨幣の銅銭が流通貨幣として用いられていた。従って天正15年以降も存続していた城なら大判小判が出土する可能性は残る。ところがどっこい、富山県の中世城郭の約96%は天正13年以前に廃城になっているのである。これでは大判小判が出土するはずがない。
「ほぼウソ」の裏返しは「少しはホント」である。チッポケな話だが、僅かながら確認されている実話を紹介したい。
平成6年鳥越城(石川県)で発掘調査中、本丸から2.5㎝×1.9㎝、厚さ1.2mm、約10gの金片が出土した。柔らかく、小刀で切った痕跡が確認されたので、小さく切り取って軍資金として使用していたのであろう。金の相場は1g約7千円なので、7万円相当の金塊と言えよう。
話は古くなるが、明治39年尾崎城(岐阜県高山市)で記念碑建立中、土中から宋銭約6万7千枚が出土している。これぞまさしく中世城郭からの埋蔵金発見の御手本のような事例である。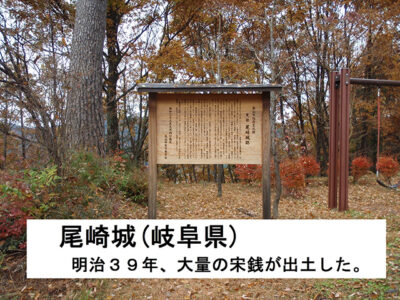 宋銭は現在1枚約500円で取引されているので、約3350万円の価値に相当する。宋銭は銅銭なので古汚く、置き場所に困るだけで、とても筆者はほしいとは思わない。
宋銭は現在1枚約500円で取引されているので、約3350万円の価値に相当する。宋銭は銅銭なので古汚く、置き場所に困るだけで、とても筆者はほしいとは思わない。
これが埋蔵金伝説の実態である。今後も見つかる可能性は低いが、仮に見つかったとして遺失物、つまり落し物扱いされるので、発見者は1割しか取得できない。このように不合理極まりない法律が、埋蔵金を発見できない一因になっているのかもしれない。