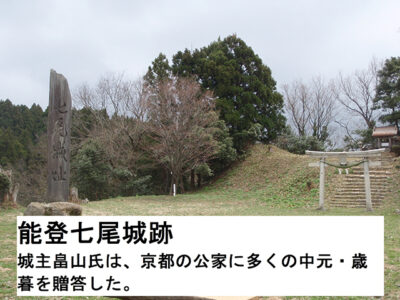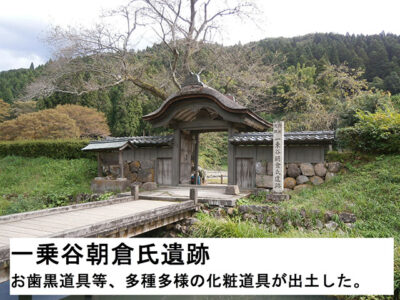佐伯哲也のお城てくてく物語 第11回
佐伯哲也の お城てくてく物語
第11回 加賀百姓共和国はウソ
長享2年(1488)加賀守護富樫正親を居城の高尾城(石川県金沢市)で滅亡させた加賀一向一揆は「百姓ノ持タル国」と言われるように加賀百姓共和国を樹立した、とされている。しかし、現実は全く違っていた。
まず加賀一向一揆は、正親の大伯父で元加賀守護の泰高を総大将に推戴する。つまり名目上、守護対元守護という構図になったわけである。当時の一揆軍は脆弱で、守護を単独で攻め滅ぼすなど到底不可能だったのである。
正親を滅ぼすことに成功した一揆軍だが、これで加賀守護そのものが廃絶したわけではない。泰高が守護に再任され、以降守護職は泰高の孫の稙泰に受け継がれていく。なんのことはない、正親が泰高に替わっただけで、加賀は室町幕府体制によって支配され続けるのである。
筆者が思う共和国とは、各集落から代議員(代表者)を1人選出し、その代議員が一ヶ所に集まり議長を選出する。そして議長主導のもと一年間の国の運営について協議する。これが共和国と思う。確かに天文15年(1546)に設立された加賀一向一揆の拠点・金沢御堂(御坊)は、各集落から「旗本」と呼ばれる代表者を選出する。しかし、運営方針は全て金沢御堂が決定し、旗本は御堂の指示通りに動く家来でしかなかったのである。この運営は、天正8年織田軍進攻による金沢御堂陥落まで続く。従って加賀百姓共和国など、どこにも存在しなかったのである。
挙句の果てに加賀国支配権を巡って、金沢御堂と本願寺から派遣された家臣(内衆)が内部闘争を繰り広げる始末である。あまりにも傍若無人な振る舞いをする内衆を、本願寺顕如自ら処罰する有様だった。百姓共和国を夢見て立ちあがった領民たちは、醜い権力闘争に終始する一揆幹部達を、どのような思いで見つめていたのであろうか。
高尾城は、富樫正親終焉の地として知られる。間違いではないが、単純ながら虎口と畝状空堀群を備えており、明らかに16世紀末の遺構である。恐らく天正8年織田軍加賀進攻に備えて一向一揆が構築し、金沢御堂の出城としての役割を担っていたと考えられる。同時に、一揆軍は高度な築城技術を保持していたことも判明する。好むと好まざるとにかかわらず。もはや一揆軍は百姓集団ではなく、純然たる軍事集団だったのである。